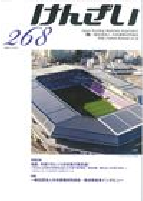-
2025年8月27日【建築・建材展大阪2025セミナー】
協力:日本建築協会
「夏季の寝室における温熱環境と睡眠の質」
梅宮 典子 氏
大阪公立大学 名誉教授
よい睡眠のための適切な冷房の使い方を追求する
過去30年で熱帯夜は急激に増えています。特に大阪は、昼の暑さでは全国12都市中第2位、夜の暑さでは第4位で、昼夜ともに高温であることから「日本一暑い」と言われています。そうなると心配なのが熱中症です。熱中症の症状には、熱失神(血圧低下)、熱けいれん(血中塩分濃度低下)、熱疲労(脱水)などがありますが、最も恐ろしいのが熱射病(体温上昇)で、こうなるとすぐに救急車を呼ぶ必要があります。気温と熱中症搬送者数には明確な相関関係があり、毎年約1,500人が熱中症で亡くなっています。政府はこれを重く見て、閣議決定により熱中症を半減させるという目標を立てました。 環境省が行った調査では、熱帯夜(最低外気温25℃以上)では4人に1人が覚醒しますが、冷房使用下のほうが覚醒割合が高いことが判明しました。従って必ずしも冷房を使ったほうが睡眠の質が向上する(覚醒が減る)わけではないことが読み取れます。 では、『よい睡眠のための適切な冷房の使い方とはどのようなものなのか?』これを調べるために、実験研究が行われました。ダイキンの新井氏らが実施した実験では、睡眠中の深部体温の変動に合わせて室温をV字変化させると、深睡眠時間が増加することが明らかになりました。別グループの垣鍔氏らが行った実験では、「就寝時26℃→起床時28℃」および「28℃→26℃→28℃(V字変化)」という条件下で最もよい睡眠効率が得られました。 これらの実験は、人工気候室という、精密な測定器が多数設置された特殊な部屋で被験者に寝てもらい行うものです。しかし実際の寝室環境は、ベッドや布団の違い、複数人での就寝、窓からの日射など様々な要因が複雑に絡み合っています。
夏季の睡眠に関する実態調査
調査方法と分析対象
睡眠時の通風・冷房・扇風機の利用頻度調査では、「窓を開けて寝ることが多い」「日によって開ける」人が約5割に達しました。われわれはこの辺りについても分析したいと考え、実態調査を実施しました。 寝室がプライベートな空間であることを考慮し、センサーと調査票を郵送して被験者自身が設置する方法を採用。7日間連続で測定を行い冷房使用や窓開放、睡眠の時間を日誌に記録し、睡眠の質は「OSA睡眠調査票」という日本で開発され臨床でもよく使われている調査票を使用、15項目の質問に4段階で毎朝回答してもらい、「疲労回復」「入眠・睡眠維持」など5因子の得点を算出しました。この5因子の平均得点を「OSA総合得点」と呼ぶことにします。調査対象は大阪市と堺市の集合住宅に住む方々、延べ266人×7晩ですが、さまざまな条件から使えないデータは半分ほど除外しています。
分析1.寝室における温熱環境調節行為と睡眠の質
温熱環境調節行為で出現頻度が高かった上位3パターンは、①全時間に冷房のみ使用、②全時間に通風のみ使用、③冷房のみを一時使用 となりました(図1)。この①②③を比較していきます。 睡眠時平均外気温や睡眠時平均室温は①②③のあいだで統計的に有意差(暑い日は冷房、涼しい日は窓開放)が出ましたが、温冷感(起床時に前夜どのくらい暑いと感じたか)では差がありませんでした。OSA総合得点(睡眠の質)では、環境省の調査と同様に①が最も悪くなりました。 着衣断熱量と睡眠の質の関係では、②の通風と③の一時的冷房の人にとっては薄着のほうが睡眠の質がよく、①の全時間冷房では薄着でも厚着でも睡眠の質に関係がないという結果でした。 外気温と睡眠の質の関係では、①②③を合計すると外気温が高いほうがやや睡眠の質がよいのですが、②と③を比較したとき、外気温27.9℃までは②のほうが睡眠の質がよく、そこを超えると逆転しました(図2)。従って平均外気温が27.9℃を上回る晩は一時的に冷房を使ったほうがよいということです。 室内の温熱環境をSET*(エスイーティスター:室温だけでなく湿度や風速や着衣断熱量なども考慮した総合指標)で表すと、睡眠の質は、①では室内SET*と関係せず、②では29℃台で最もよく、③では30℃から31℃台でよいという結果が得られました。

図1 寝室における温熱環境調節行為の出現頻度 
図2 温熱環境中位における外気温と睡眠の質 分析1.結論(まとめ)
睡眠の質は②全時間通風の人が最もよいという結果が出ました。①全時間冷房の人は、温熱環境と関係なく睡眠が悪いという結果。分析2.住戸の熱的性能と睡眠の質
間取りや住戸位置、住戸面積などの住戸属性は睡眠の質とあまり相関性がありません。ところが寝室窓方位や、「日射熱の煩わしさ」や「日射しの眩しさ」の主観評価など熱的性能に関しては睡眠維持の因子で大きな相関が見られました。そして、関係があるのではないか? と思われた風通し、眺望、外気清浄度は関係ありませんでした。 新しい住戸ほど断熱性能が高いと仮定したのですが、新しい住戸ほど疲労回復因子の得点が高いことが分かります。この疲労回復に関しては、主観評価「暖房の効きや冷房の効きがよい」ほど高い得点が出ています。また、冷房を使用する場合は、冷房設定温度が高いほど疲労回復得点が高いことも分かりました。 次に、入眠・睡眠維持得点と日射遮蔽性能の関係を分析しました。これがいわゆる覚醒に関わるデータです。南・東・西という寝室窓方位で比較すると、東向きで冷房を使わなかった場合の得点が低く出ました。「日射熱の煩わしさ」も冷房不使用の場合に低得点でした。従って、入眠・睡眠維持得点は日射遮蔽性能と関係があり、特に冷房不使用時に大きく関係してくると言えます。室温も調べましたが、やはり東向きは高温でした。 疲労回復因子得点と住戸の断熱性能の関係では、古い住戸つまり断熱性能が低い住戸で、冷房を一時的に使用する人(タイマーなど)の得点が極端に低くなりました。興味深いのは、同じ古い住戸で冷房使用が高頻度の人と不使用の人が同じぐらいの高得点になっていることでした。整理すると、疲労回復得点は冷房使用が低頻度の場合のみ断熱性能と関係してくると言えます。 睡眠時の室温上昇と断熱性能の関係を見ると、冷房を一時使用した場合にのみ、古い住戸ほど睡眠時の室温上昇が大きい、という結果が得られました(図3)。ここで室温上昇とは起床前3時間の平均室温から就床後3時間の平均室温の差のことです。疲労回復得点は室温上昇が1℃の時点で下がり始めることが分かります。古い住戸に関しては、ずっと冷房するか(高い設定温度で)、むしろ一切冷房を不使用にするほうが疲労回復によいということになります。

図3 睡眠時の室温上昇と断熱性能や設定温度 分析2.結論(まとめ)
1) 冷房を一時的に使う場合は、全時間冷房や全時間通風とは異なって、住戸の断熱性能が低いほど、室温上昇(起床前3時間の平均室温から就床後3時間の平均室温を引いた値)が大きい。 2) 断熱性能が低い住戸で冷房を一時的に使う場合、冷房設定温度が低いほど室温上昇が大きい。 3) 室温上昇が1℃を超えると疲労回復得点が下がる。 4) 冷房を使わない場合、寝室窓が東向きのときに南・西向きと比較し室温が高くなり、入眠・睡眠維持因子得点が下がる。 今回の分析データは2014年から地道に取ってきたものですが、お盆なども含む盛夏期にしか取れないデータであるため、当時の学生らの尽力なしには実現できない調査でした。我々はこの調査以外にも、就寝後の室温変化や、盛夏期と残暑期の睡眠の質の違い、年齢など居住者の属性の違いにフォーカスした調査、ほかいろいろな調査を試みています。今回の調査と分析が、皆さまのよい睡眠のお役に立つことができれば幸いです。