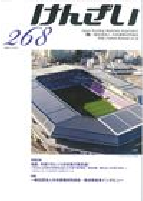-
2025年8月26日【建築・建材展大阪2025セミナー】
協力:大阪府建築士会
「ZEBとカーボンニュートラルの実現に向けて今できること」
岩岸 克浩 氏
大阪府建築士会 理事
建築基準法の改正と省エネ基準の適合義務化
2025年4月に施行された建築基準法の改正について紹介します。まずは、2050年のカーボンニュートラル、2030年の温暖温室効果ガス46%削減に向け、2050年にストック平均でZEH・ZEBの基準を引き上げ、なおかつ2030年にZEH・ZEB基準の省エネ性能を目指すという取り組みが進められています。 2025年3月までは300㎡未満の建物は届出だけでよかったのですが、改正により、4月以降は全ての住宅・建築物で「適合義務」となり、省エネ計算なしでは確認申請が通らなくなりました(図1)。一方で省エネ改修にあたり制限の緩和が設けられることになります(後述)。加えて木材の利用促進のための建築基準の合理化も進められています。

図1 省エネ基準適合義務制度 義務付けの対象 省エネ基準はアクティブとパッシブ両方でクリア
省エネ基準の適合義務は、当然増改築でも課せられ、適用範囲は増改築する部分のみとなっています。設備機器の性能向上で省エネ基準をクリアするのは難しく、パッシブ(断熱など)でのクリアが重要になります。 省エネ基準について、住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準の両方、非住宅では一次エネルギー消費量基準に適合する必要があります。非住宅の申請時に外皮部分は不要ではありますが、これは断熱なしでクリアできるという意味ではありません。断熱の施工精度が低いと、計算上はクリアしていても実際は適合していないものと同様となってしまうのでご注意ください。 住宅の外皮性能は、「UA値」と「η(イータ)AC値」で表され、地域区分別(大阪は4)に規定された基準値以下が求められます。値が小さいほど熱が入りにくい、すなわち断熱性能が高いと判断されます。UA値とηAC値を所定の計算法で算出しますが、以前は全面の数値が必要で、精度の高い計算が求められていました。今は代表的な1面だけの抜粋でも可能になり、申請のハードルは下がっています。 一次エネルギー消費性能は、住宅・非住宅共に「BEI値」で表され、1.0以下になることが必要です。自分が設計したエネルギー消費量「設計一次エネルギー消費量」を、一般モデルとなっている「基準一次エネルギー消費量」で割った値を1以下にするというわけです。1を下回ると当然役所では受け付けてくれません。非住宅では2024年4月に「基準一次エネルギー消費量」の数値が下がり、BEI1.0以下をクリアするのが難しくなりました。この数値は今後も厳しくなっていくので、同じ施工をするのであれば早い時期に実行してクリアすることをおすすめします。
「4号建築物」が廃止、「新3号建築物」に
建築基準法の改正で、「4号建築物」が廃止され、「新3号建築物」となりました。比較的小さな建築物は「新3号」のカテゴリになり、省エネ適合判定を簡略化できる仕組みが導入されました。これに該当するのは、「省エネ適判を行うことが比較的容易な特定建築行為」の①~③のいずれかに限られます。
①仕様基準を満たす住宅
②設計住宅性能評価を受けた新築住宅
③長期優良住宅の建築等計画の認定または長期使用構造等の確認を受けた新築住宅
また、設計住宅性能評価を活用した省エネ適判の審査の合理化も行われています。フラット35SやBELSなどの評価を活用しても同様に適用されます。再エネ設備の設置で制限緩和の特例許可
国交省は脱炭素社会の実現に向け、建築物の再生可能エネルギー利用を促進するための制度の改正を行いました。これは、制定された「建築物再生可能エネルギー利用促進区域」の中で建築規制の緩和が受けられるというもの。建築士から建築主へ設置可能な再エネ設備を説明し、合理的に認められるのであれば、その部分を建築面積や容積から抜くことができるという緩和です。 そのために設けられたのが特例許可制度です。要件に適合する建築物が特例許可の対象になります。例えば太陽光パネルの設置で高さ制限を超える場合でも、促進区域の趣旨に鑑みて、建築物本体の影から影を増やさない、あるいは敷地外に影響しないことが認められれば、制限を緩和してもらえます(図2)。 ここまでの省エネ適判は建築士には説明義務があり、建築主の理解を得た上で両者が省エネを目指していくことがポイントになります。

図2 再エネ促進区域における特例許可の創設 既存建築の改修にも特例許可制度や補助金あり
既存建築ストックに対しても省エネ改修を進めるための特例許可制度があります。例えば屋根の断熱改修や屋根の再エネ設備設置で構造上やむを得ず高さ制限に抵触するような場合でも、特例でクリアできます。建ぺい率や容積率に関する特例もあり、例えば日射遮蔽のために庇を大きく張り出す場合でも、効果が得られるならば建ぺい率への不算入が可能なケースもあります。また、共同住宅の共用廊下にヒートポンプ式給湯器を設置する際の容積率の特例許可も活用できます。 費用面の支援として、グリーンリフォームローンという融資制度があり、最大500万円まで担保不要で利用できるので、このような補助金を上手に利用しながら改修するのがよいでしょう。
カーボンニュートラルに向けた取り組み
建築物が今、ZEH・ZEBに向かっているのは、国が2050年のカーボンニュートラル、そして2030年の温室効果ガス46%削減を目指すことを宣言したからです。実際の削減実績は2021年度で19.8%減なので、このままでは実現が難しく、取り組みの加速化が必要です。特に民生部門の建築に要求されるハードルが上がってきています。国では2030年、2050年に目指すべき建築物の姿として、ZEB基準の省エネ性能の確保を謳っています。 ZEBには、エネルギー削減率の高い順から「ZEB(Net Zero)」「Nearly ZEB」「ZEB Ready」「ZEB Oriented」にランク分けされています(図3)。現在、民生部門より公共施設のほうがエネルギー使用量が多いため、公共施設におけるZEB化がより求められています。 新築建築物の環境性能データを見ると、省エネ基準適合率(2023年度)が住宅で89.9%、非住宅で99.6%まできています。同年のZEH・ZEB水準の適合率は、住宅で46.1%、非住宅で37.4%なので、ZEH・ZEBのレベルアップを今まさに頑張っているわけです。

図3 ZEBの省エネ、創エネ度合いとZEBランクの関係図 今後のZEB設計のためのお役立ち情報
(財)環境共生イニシアチブでは「ZEB設計ガイドライン」を公開しているので、ダウンロードして設計に盛り込んでください。同ガイドラインには、建物用途別(事務所、老人ホーム、スーパーマーケット、病院など)の設計手法が掲載されています。これを参照することで若干ハードルが下がるかと思います。 事例研究については「公共建築物におけるZEB事例研究」に興味深い事例分析が掲載されています。規模別では2,000㎡程度の建物がZEBになりやすく、用途別では事務所ビルが最も実現しやすいようです。 大阪府は2025年3月に、断熱性能を見える化するツールを公表しました。エクセルデータにラジオボタンで入力するスタイルで、これを使えば省エネ性能の計算や概算コストの算出が可能です。大阪府の発行したZEB事例集の冊子もぜひ参考にしていただければと思います。