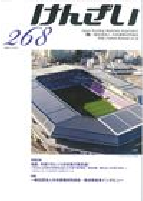-
2025年8月25日【建築・建材展大阪2025セミナー】
オープニングセミナー
「万博はどんな建築の未来を見せるのか?―建築史家が語る大阪・関西万博2025の意義」
倉方 俊輔 氏
大阪公立大学 教授
万博のシンボル、人がいるほど映える大屋根リング
私は建築史家で、ものづくりの現場からは離れたところにいます。今日はそんな、いわば第三者といえる目線で大阪・関西万博を考えてみましょう。 まず大屋根リングです。キャラクターのミャクミャクと並んで万博で一番の人気を誇っていますよね。大屋根リングは、会場デザインプロデューサーで建築家の藤本壮介さんが手掛けた世界最大の木造構築物です。これは単独の存在ではなくて、会場全体の配置計画と連動して設計されています。東西を結ぶ横の軸線の中央に「静けさの森」が位置しています。それに直交する縦の軸線には今回の万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」に呼応する8通りのパビリオンが並ぶ「シグネチャーゾーン」があります。その他のリングの内側には海外のパビリオン、外側にはその他の組織や日本関連のパビリオンを配置されているのです。 大屋根リングを目の目にすると「見たことのない光景だ」という印象を抱くと思います。1周約2km、と聞くと巨大さに圧倒されるかもしれません。けれど実際は、材料が木なので親しみがわいてきます。壁や内部空間があるわけではないので、これは建築と言えるのか? 私は建築だと考えます。なぜなら、人の体感を変化させる構築物であるからです。 下に入ると屋根がかかって軒下にいる状態になり、外の光がより強調されて感じられるなど、外部にいるのとは違う感覚が得られます。大屋根リングは109個の架構ユニットで構成され、それぞれに番号が振られて、場所の目印の役割も果たしています。無秩序にサインや看板が貼られた日本の街なかとは違い、スマートなサインシステムとなっているのです。 万博がスタートして如実に感じたのが、大屋根リングは人が入った状態のほうが断然よいということ。たくさんの人が入ることでリングの大きさがより実感され、人々は自然と上に登ったり歩いたりする様子も楽しいものです。大屋根リングの存在こそが、こうした行動を誘発しているのです。 4月13日の開幕セレモニーとして行われた「1万人の第九EXPO2025」は実に壮観で、今回の万博のよさが建築物やパビリオン単体にあるのではなく、人間の生き生きとした振る舞いにあるのだということを実感させられました。人間の営みの素晴らしさを感じさせるのがこの万博の目的であり、それを支える「縁の下の力持ち」が建築である素晴らしさに思い至ります(図1)。

図1 開幕セレモニー「1万人の第九EXPO2025」の様子 材料をリユースできるパビリオン設計
大屋根リングも含め、今回の万博では建築材料が大活躍しています。70年万博では基本的に再利用が考慮されていませんでしたが、今回は多くのパビリオンが材料の調達から廃棄・再利用までを考慮しており、そこに社会の進歩の反映を見ることができます。建材の集積として建築がつくられ、それがもう一度建材として再利用される、まさにリサイクル、リユース時代の万博であるわけです。 建築家の永山祐子さんが設計したパナソニック館「ノモの国」は、鉄パイプを立体的に組み合わせたユニット構造で、その間に取り付けられたオーガンジーの布が風に揺れます。もちろん後で解体して再利用できるようになっています。しかも建築のみならず家具や遊具に転用可能です。同じ建材が用途だけを変えて活躍を続ける、これが最先端の考え方であることが万博を通じて伝わってきます(図2)。 永山さんは、また「ウーマンズパビリオン」の設計者でもあります。これはドバイ万博で永山さんが手掛けた日本館に使用された建材をリユースするという、万博の歴史で初の試みです。同パビリオンはドバイの日本館とは形状が異なりますが、ボールジョイントのユニットや布などが再利用されました。このようなリユースは、単に環境に配慮するだけでなく、よりクリエイティブで楽しいものづくりにつながることを教えられます。もう一つ注目すべきは、70年万博では建築設計者は全員男性だったのが、女性が設計するのも当たり前の時代になったという進歩です。

図2 再生可能なユニットを使用したパナソニック館「ノモの国」 若手建築家のアイデアが光ったトイレ、休憩所
今回、40歳以下の若手建築家20組がオールジェンダートイレやポップアップステージ、休憩所を手掛けたことも画期的でした。若手がいろいろなアイデアを出し、それを藤本さんらがセレクトした上で実現させました。 子どもに大人気のとある休憩所では、環境に配慮して残土を出さない設計が試みられました。また別の休憩所は、倉庫に眠っていた播州織の織物を使った屋根が、まるで風にふんわり舞うような形になっています。ここでも子どもたちが大はしゃぎで遊び回っている様子が見られます。こうした点も、今回の万博が家族で楽しめるものになっている要因だと思います。 若手建築家が3人グループでつくったオールジェンダートイレは、入口と出口が異なるため最初のうちは仕組みを分かっていない人々が混乱し、半分ぐらい故障して批判も出ていました。最近は皆さんも使い方を理解して、混乱は治まっているようです。トイレを出ると中庭が広がっており、清々しい気分を味わえます。このような新しいアイデアの設計を見ていると、今の日本はまだまだ変化を恐れており、そのため他の国々に後れをとっている部分もなきにしもあらず……と感じます。人間の適応力をもっと信頼して、今の時代だからこそ提供できる楽しさや新しさを若手にどんどん考えていってもらいたい。そんな良い方向性に日本が向かう契機にも、今回の万博はなるのではないでしょうか。
若手が経験を積める機会を提供することが重要
「2億円トイレ」として有名になったトイレは、最初「2億円」という報道だけが一人歩きしていましたが、最近ではむしろ愛称になっています。個室の集合体がカラフルに彩色されて積み木のようにも見えます。手洗い場は外壁に蛇口が取り付けられた簡素なつくりですが、最近はすっかり人気になって子どもが手を洗う様子を両親が楽しそうに撮影している姿が見られます。 オールジェンダーなので手洗い場も男女共用で外部に露出しているわけですが、面白いのが、手を洗う光景って悪いものじゃないなと思えてくることです。部材は組み替え可能で、会期後に別のユニットと組み合わせて休憩所にするもよし、トイレとして使うのもよし。工業化を受け止めたつくりでありながら、子どもが積み木を組み替えるような原初的な楽しさも感じさせます(図3)。 大阪城のために切り出されたが運ばれなかった「残念石」を使ったトイレも、文化財の扱いについて批判を受けました。しかし私は、この石に刻まれた歴史が多くの人に知られる機会になったことを歴史家の目線から評価したいと思います。 日本では実績のある人や年長者が決定権を持つことが多く、若い世代が挑戦する機会が限られています。今回の試みのように、若手に設計機会を提供し、利用者に喜ばれたり、ときには批判にさらされたりする経験を通じて成長してもらうことが重要ではないでしょうか。 今回の万博を通して感じたのは、万博が単なる建築物の展示ではなく、人間の新しい体験や行動を促す場となっていること。そして、平等や安全や環境を尊重する社会だからこそ楽しい万博が実現できたのだということ。また、デジタル技術を活用しながら人間的な体験を大切にする姿勢も大きな特徴になっていました。これらは普段、ともすれば見過ごされがちな現在のありようを具現化したものであり、その先に次の展開がある。訪れた一人ひとりが、そんな未来を見通せる好機が大阪・関西万博だと思います。

図3 カラフルな積み木のようなオールジェンダートイレ