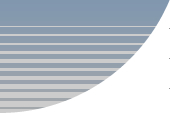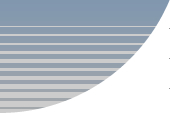 |
|
第56回
「職人不足の解消につながる生産性向上、省力化技術」
掲載情報は全て著作権の対象となります。転載等を行う場合は当協会にお問い合わせください。
|
|
|
|
|
|
|
 |
基調講演
「建築生産を取り巻く時代の大きなうねり」
木谷 宗一氏 一般社団法人日本建設業連合会 施工部会長
㈱竹中工務店 生産本部専門役
|
|
|
データが重いので右クリックしてメニューからファイルをダウンロードしてください
資料はこちら(レジュメPDFデータ)
|
|
|
■建設業を取り巻く現状と課題
はじめに「現状と課題」を概観しようと思います。出典は、国交省統計データですが、建設技能者の高齢化は深刻で、今後10年で大量離職が見込まれています(図1)。
賃金のピークは45~49歳であり、それ以降はどんどん下がります。本来は、彼らの持つノウハウやマネジメント力を評価し生かすべきですが、現実はそうなっていません。社会保険の加入状況を見ますと、ゼネコン社員はほぼ100%に近いのですが、1次、2次、3次下請けと下がるにつれて、加入率が低くなっており、これは上げていかねばなりません。一方、建設業の年間労働時間は、製造業と比較して92時間、全産業平均と比較すると年間334時間と非常に長く、格差が激しいのが現状です。休日取得状況を見ても、他産業では当たり前となっている週休二日が取れない状況にあります。
■国家施策「生産性革命」「働き方改革」「人づくり革命」
国が掲げる3本の大きな錦の御旗があります。一つは2015年末に国交省が掲げた生産性革命プロジェクト「i-Construction」です。2016年には政府未来投資会議が、建設業の生産性向上目標を20%とすることを発表しました。
もう一つは働き方改革です。政・官・財が非常に迅速に動いているのですが、特に2017年、政府から発表された「働き方改革実行計画」では、残業時間を年間720時間、月100時間未満にすることがうたわれました。法自体の施行は2019年ですが、建設業には猶予が与えられ、5年後の2024年施行となりました。それでも待ったなしです。本腰を入れて対応していかなければならない状況になりました。2019年4月、労働基準法が創設以来初めての大改正が施行され、猶予を与えられた建設業においても2024年4月には適用されます。これを受け、日建連は2022年3月までに作業所の4週8閉所を達成するという大目標を掲げました。2019年は中間目標として4週6休を何とかクリアしようと活動しています。時間外労働の上限規制を遵守するため作業所を閉所するという施策に軸足を動かしたのです。それから人づくり革命という構想です。2018年に政府から発表されました。この人づくり革命と主旨は少し異なりますが、我々は後述する「現場の人づくり」に重きを置いた活動を展開しなければならないと感じています。
■日建連「建設業の長期ビジョン」
一方、一般社団法人日本建設業連合会(日建連)は、2015年3月、「建設業の長期ビジョン」を発表し、こう述べました。1997年には464万人だった国内建設技能者が、高齢化や賃金問題などで2014年には343万人と約26%減少してしまい、このまま離職し続けると10年後の2025年には、215万人(37%減)になってしまいます。一方、(一財)建設経済研究所によると、国内建設投資額は51兆円を維持し続けると言われており、従来、東京五輪が終わったら一気に投資額は下がると言われていたのに、大きな目論見違いとなっています。51兆円をこなすには最低305万人は必要です。215万人では到底足りません。この窮状と対策への大方針を訴えるために日建連は長期ビジョンを打ち出しました。その骨子は、「90万人の入職者確保と35万人の省人化」という大きな数値目標にあります(図2)。
■2015年頃の生産性向上の考え方
生産性向上を考える上でのポイントは、誰でも使える汎用技術にするということであり、主に6つの考え方がありました。それは、1.生産性を考慮した設計の作り込み 2.工場生産による現場作業の削減 3. 仮設低減、乾式化、単純化による省人化 4. 作業の標準化(マネジメント)」5. 自動化、機械化(ロボット) 6.BIM、ICT活用 というものです。1~5は省人化、6は見える化です。技術面において特に注目されているものに、ハイブリッド構造があります。例えばセンターコアをRC壁、柱をPCa(RC)梁をSとした混合構造です。軸力を負担する柱にはコストの安いPCa(RC)を使い、長大スパンの梁にはSを使うという、材料の“いいとこ取り”をした構造です。
超高層建物では、よく小梁とデッキを組み合わせ、その下部に設備配管・ダクトなどを地上で組み込み、一気に建方してしまうフロアパネルユニットがありますが、既に当たり前の技術になっています。プレキャストコンクリート(PCa工法)では、全てをPCaにするとコストが上がるので、面倒な部分をPCaに、標準化された部分を在来工法で行っています。PCaと在来の組み合わせが目の付け所です。工場で設備機器を先付けしてユニット化する工法も、現場作業の削減や揚重回数の削減に効果的です。
■発展途上の施工BIM
2014年頃から、日建連では施工におけるBIMスタイルの事例集を作成開始しました。意匠・構造・設備の整合確認(構造体と設備の干渉チェックなど)ではよく活用されています。現場では、きちんと図面が納まっているかの確認が最も重要です。設備専門工事会社、作業所の設備担当者、意匠設計者などの関係者が一堂に集まって、モニターを見ながら調整を行うスタイルが多くなってきました。
当社の例で言うと、自社開発ソフトで、例えば鉄筋モデルを作成するのですが、これがあると鉄筋どうしの納まりは勿論、鉄骨アンカーボルトとの干渉なども事前にチェックすることができます。外装では、鉄骨とアルミルーバーのファスナーなど細かい納まりも事前に調整できます。 いずれにしても川上で事前につくり込んで現場がスタートするので、後戻りしなくてもよいわけです。そこがBIMの最大の活用ポイントとなります(図3)。
BIMの成功要因は、BIMの作成範囲を明確化することです。隅から隅までBIMにするのではなく、大事な部分だけに運用します。一方で、課題は2次元図面の作成・併用にあります。最終的には、2次元でアウトプットしますが、そこにたどり着くまでは3次元で決めていくことを徹底する必要があります。また、異種ソフト間のデータ連動ができないことも大きな課題です。事例集の2018年版では新たに人材不足、作業所へのBIM教育といった課題があげられました。
■2016年に始まった日建連施工部会の生産性向上活動
こうした背景のもと、日建連施工部会は原点に帰る意味で、1990年代からの生産性向上の歴史の俯瞰から入りました(図4)。過去を振り返ると、1990年代のバブル絶頂期、ゼネコン各社は人手不足対策として「複合化工法」の開発に取り組みました。つまり、省人化技術の開発競争は90年代から30年近い歴史の中でずっと重ねてきたのです。2013年頃からはフロントローディング、すなわち川上段階で生産情報を設計図書に反映したり、BIMやICTなどによる最先端のソフト技術を使った仕事の進め方に邁進してきました。これに加え2017年には、現場は人が大事だとの考え方に基き「魅力ある建築生産の場づくり・人づくり」を始めました。
このようなことから、2025年に「建設現場の生産性革命」を完遂させるための基本方針を 1. ハード/ソフト技術の進化および裾野拡大を図る 2. 最先端ICT技術を建築生産に取り込む 3. 魅力ある建築生産の場づくり・人づくりを推進する としました。これらを成し遂げることにより、最終的に、高い生産性を誇り、魅力ある建設産業となることを目指したのです。方針1は省人化技術の水平展開であり、方針2はデジタルファブリケーションです。方針3は人づくり革命だと考えています。今までは殆ど語られませんでしたが、方針3は業界における最重要課題だと考えています。BIMもICTも道具であり、道具を使うのは人です。その人を育成しなければなりません。図面が描けない、読めない若手が山ほどおり各社共通の悩みになっています。現場を管理する人間がこれではどうしようもありません。施工図を外注に任せてしまっているようでは本当の意味での品質管理はできません。それから作業所長のマネジメント力に着目しています。生産性向上における最も重要な要素は作業所長だと考えているからです。
■日建連の活動事例の紹介<4事例>
○担い手の確保・育成からマネジメント力向上のために
現場の最前線を担っている人達、特にこれから作業所長になっていく人達のために、日建連会員各社から推薦された作業所長さんから、さらに優れたマネジメント力を発揮している4人の作業所長さんを厳選し、毎年講演会でスピーチをして貰っています。2016年から始まり、年々聴講者が増え、2018年には310名の参画を戴きました。4人の方々には事前に座談会に出席戴きお話を聞くのですが、その時の詳細な記録を講演会に際に皆さんに配付しています(図5)。
先ほど図面力の重要性について触れましたが、いま「スケッチコミュニケーション」という活動を会員各社に取り組んでもらっています。実は、これは第2回の講演会(2017年)の際に、ある所長さんが語ったことなのですが、若手現場員に5mm方眼のノートを渡して手描きのスケッチを描かせ、それをもとに現場の納まりや作業手順について会話していると言われたのです。自らの技術の根っこを失ってしまっては本末転倒です。スケッチこそ“ものづくり”の根幹であり、施工者の『図面力』を維持向上することは極めて大事です。多くの人達が、これは素晴らしいと感銘し、一気に輪が広がりました。
○省人化ハード技術+お手軽便利なICTツール
日建連ウェブサイトの「建築」ページを見ると、私達が取り組んでいる生産性向上活動の一端を見ることができます。当初、生産性向上専門部会のメンバー15社に、公表できる省人化ハード技術を全て出すよう依頼して、約340件の事例を集めました。そこから108事例を選び、仮設から特殊工法まで幅広くシート化し、ホームページに公開しました。
もう一つはソフト技術です。デジタルファブリケーションと称して、デジタル化の波を大きく第1~第3世代で分類しています。第1世代はモバイル活用です。いまは第2世代に差し掛かっていると思いますが施工BIMのフル活用が中心になりつつあります。そのような時代に我々は何をするか。まずは業界として共有できるモバイル技術を整理しようということから、42の市販アプリを選定し「お手軽便利なICTツール」として普及・展開を図ることにしました。これも日建連ホームページに公開されています。
○建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン
(国交省)+建築工事適正工期算定プログラム(日建連版)表題にあるガイドラインは、2017年8月に国交省をはじめとする関係省庁連絡会議により纏められたものです。この中には、建設業の生産性向上など自助努力は勿論大事だが、発注者の取り組みも必要であると書かれています。工程管理がきちんとできている現場は品質、安全全てにおいて問題が起きません。できていない現場は常にバタバタし、品質も安全もおろそかになっています。いかに適正な工期が獲得できるかは極めて重要です。時間外労働時間の上限枠等についても書かれていますが、やはり発注者から理解を得なければならないと感じています。
ガイドラインには、建築工事の適正工期の指標として、日建連「建築工事適正工期算定プログラム」の適宜参考として活用することが明記されました。これは日建連施工部会、5年前から開発を始めたものであり、工期というものに対する一つの公的な物差しをつくったことに最大の意義があります。それまでは標準工期というものがありませんでした。いまはプログラム普及のために国交省と地方自治体には無料で使用してもらっています。建設業法の改正が取り沙汰されていますが、法制化された暁には、受注者(ゼネコン)の工期ダンピングおよび発注者による適正工期での契約が義務付けられます。違反した場合には勧告処分が下されることになると報道されています。私達は、元請適正工期を「日建連適正工期(ベースとなる適正工期)+プロジェクト特性を踏まえた工期増分-生産性向上努力を施した工期短縮分」として定義しています(図6)。契約工期と4週8閉所を組み込んだ元請適正工期が一致することを望んでいます。そうすれば労働基準法適用となる2024年4月から2年前倒しの2022年3月までには4週8休の実現も可能でありますし、時間外労働時間の上限規制にも対応できると考えています。
○建築生産用ロボット技術開発の取り組み
1980から2000年頃にかけて、各社ともロボット開発を積極的に推進しました。過去の反省点を整理すると、「適用範囲に制限あり」「設置・組解体が手間」「スペックミス、性能不足」といった不満点が目立っていました。そこで過去の反省点を踏まえ、次の四つの方針を掲げました。すなわち、1. 徹底的に作業員の立場に立って考える 2. 自動化を求めすぎて複雑な機構とせず、作業員が容易に取り扱えるものとする 3.高度な技能を有する作業は人に任せ、機械はそのサポートに徹する 4.技能を要しない作業は、最大限機械化を図る以上の4点です。これらを踏まえた最近の取り組み事例としては、ICTクレーン、ICT場内運搬、ハンドリング機、高機能高所作業車、マッスルスーツ(重い物の上げ下ろし補助)、位置認証などがあります。私の所属する会社では、人の後を付いて歩き運搬作業の省力化を可能にする自動追従台車や揚重機能付き高所作業車、耐火被覆ゴミかき集めロボなどを開発しています(図7)。同様のコンセプトのロボットが、他大手ゼネコンでも多数開発されています。業界を問わず、ロボットに対する期待はますます高まっています。ロボット技術開発を一過性のものとして終わらせないために、業界全体で継続していくことが重要だと思います(図8)。
生産性は、2015年を0としたとき、2017年は9%向上したと我々は考えています。これは新築工事の完工高と1日当たり建設技能者数から割り出した指標です。しかし、ここから20%まで持っていくのは至難の業であり、相当な努力が必要であると思います。生産性向上という切り口の中で、ぜひ省人化できるような開発を皆さまには是非お願いしたく思います。
|
|
 |
「鉄骨耐火被覆材の最新動向」
重野 誠治氏 エスケー化研㈱ 耐火断熱営業部 部長
|
|
データが重いので右クリックしてメニューからファイルをダウンロードしてください
資料はこちら(PDFデータ) |
|
|
■鉄骨の構造材を火災の熱から守る耐火被覆材
当社は建築塗材のメーカーですが、1980年のアスベスト全廃を受けて1985年、耐火被覆材の市場に参入しました。2000年からは耐火塗料の市場にも参画しています。鉄骨耐火被覆材とは、火災時の温度上昇を防ぐために鉄骨の柱、梁など構造材に施すものです。鉄は350~400℃の高温で熱されると強度が落ちます。2000年に導入されたISOでは500℃くらいといわれています。
2001年の「9.11」で鉄骨造がみるみるうちに倒壊していった光景を皆さんも見たと思います。耐火建築物、防火・準防火地域、階数、延床面積で耐火構造が決定されます。耐火時間は、梁柱の1時間、2時間、3時間と、柱だけを被覆する30分の認定もあります。
■耐火塗料の市場シェアはわずか1%
最近10年の着工床面積推移を見ると、鉄骨造が約5,000万㎡、RC造が約2,200万㎡となっており、着工床面積構成比でみると鉄骨造38%に対してRC造が17%と、鉄骨造の割合が高いことが分かります。耐火被覆材の施工面積は増加傾向にあります。鉄骨需要量と耐火被覆を必要とする建築物から換算すると、2,700万㎡/年と推定されます。
この2,700万㎡の中で最も使われているのは吹付ロックウールで74%。吹付ロックウールとは鉄鋼のスラブを粉砕してセメントと混ぜたものです。最近増えてきたのがブランケットタイプのマキベエで16%。
次にケイカル(ケイ酸カルシウム)板が6%、当社でも扱っている湿式のセラミック系吹付が3%。そして本日特にご紹介する耐火塗料、これはわずか1%の市場です(図1)。請負金額シェア(単価ベースでの換算で500億円)で見ると、吹付ロックウール57%、マキベエ21%、ケイカル板10%、セラミック系吹付4%です。注目いただきたいのは耐火塗料の8%。要するに、汎用性の高い吹付ロックウールは安価であり、マキベエや耐火塗料は高価であるというわけです(図2)。
■鉄骨造、耐火被覆は増加する一方で職人は減少
耐火塗料とは火災時に発泡して炭化層をつくり、鉄骨を熱から守るものです。柱などに吹付けて施工します。高価な製品なので、意匠性の高いあらわしの構造材に使われることがほとんどです。
耐火被覆工事では、シェアの高い吹付ロックウールは吹付け時に粉塵が多く、施工環境がよくないため、マキベエのような乾式工法も採用されつつありますが、コストの関係で結局またロックウールに戻ってくるといった繰り返しが延々と変わらず続いているのが現状です。しかし吹付ロックウールを扱う職人は高齢化で減少し、若者も施工環境の悪い仕事からは離れていっています。鉄骨造は増えているが耐火被覆工は減少していくのではないかと思います。
そこで吹き付けのロボット化が各ゼネコンで考えられています。全てをロボットに頼ることはできませんが、人員を減らせるというメリットがあります。
■海外では耐火塗料のシェアが50%
海外で行われた市場調査のレポート(2017年)をご紹介します。海外(北米、欧州、アジアパシフィック先進国)では、2016年に2,500億円だった市場規模が、2023年までに3,200億円に拡大すると推測されています。その中で、日本で1%しかない耐火塗料のシェアが耐火被覆材の50%を占めています。残りはセメント系です。
プラント火災を想定したハイドロカーボン火災向けの耐火被覆が一般建築向けとほぼ同規模であることも日本と大きく異なります。
また、現場で施工せずにファブリケーターでプレコートするオフサイトという施工方法が増えているのも特徴です。そしてガラスカーテンウォール、鉄骨むき出しのデザインに耐火塗料が求められているそうです。
オランダのアクゾノーベルコーティング(株)提供による鉄骨ファブリケーターでの施工写真をご覧ください(図3)。2液混合タイプの製品で、このように大型機械を用います。ファブリケーターで施工し、その鉄骨を現場に運ぶという流れです。これが海外では主流になりつつある手法です。
■プレコート工法は現場の省力化に最適
今後、現場の省力化を考えていくなかでご提案したいのが、耐火塗料のプレコート工法です。
ファブリケーターで施工すると、現場ではジョイントや傷部の施工のみで済むため、他工種との同時施工が可能になります。これは吹き付けの耐火被覆が忌避されている現状では大きなメリットです。
材料のイニシャルコストは吹付ロックウールに比べると高く、またファブリケーターで塗装ブースを持っていない場合は横持ち塗装(他の場所に運んでの塗装)になりますが、それらのコストを考慮しても、省力化ができる究極の工法だと考えています。最近ではいろいろなゼネコンの現場でプレコート工法が導入されています。
実際に鉄骨ファブリケーターで施工しているようすをご紹介します。
まず下地調整で、鉄骨のケレン作業を行います。ジョイント部分はベビーサンダーを使って研磨。鉄骨の下地処理がしっかりしていないと、製品の品質が安定しないので、これは重要な部分です。
ファブリケーターの塗装ブースの中で、エアレススプレーによる防錆塗料施工を行います。ジョイント部分は刷毛でしっかり塗装しています。
ウェット時の膜厚はウェットゲージという道具で管理し、乾燥後は電磁膜厚計で管理します。
施工は、非常に大きな塗装ブースの中で行います。しかし、こうした施工が可能なしっかりした塗装ブースを所有するファブリケーターは全国で10社程度しかありません。ブースがない場合は通常、屋外で行うのですが、屋外での施工は品質管理が難しく、安定した品質を保つことができません。
下地と防錆が完了すると耐火塗料を塗布します。塗装ブースで、発泡層となる主材およびトップコートを施工して完了(図4)。ジョイント部は養生が必要です。
これでようやく塗装ブースからファブリケーターのヤードに搬出します。トラックでの移動です。そしてヤードから現場に出荷されていくわけです。
■耐火塗料のプレコート工法普及のための材料開発
鉄骨ファブリケーターで耐火塗料を施工して現場に運ぶ過程で、様々な問題点が明らかになりました。それらの問題点解決のためには、材料開発しか道はありません。先ほど海外市場について触れましたが、海外ではプレコートが主流になりつつあるため、トラックで搬送するときに生じる振動への追従性や雨養生などを考慮した製品開発も行われています。
一方で日本の耐火塗料は、残念ながら現状では1液タイプのものが主流で、振動への追従性や耐水性がどうしても不十分でした。今後、現場の省力化を考えるなら、やはりプレコートが必要になってくるでしょう。そしてプレコート工法を普及させるためには、耐火塗料の性能をアップさせるための材料開発をしなければなりません。
そこで当社は、2液反応硬化型耐火塗料「SKタイカコートHS」を開発しました。現在はまだ柱の1時間耐火のみの認定ですが、今後は梁、2時間や3時間の認定も取得する予定です。
従来の1液タイプとの比較をご覧ください(図5)。まず厚付け性がより高いこと。従来品はタレやすく、ウェットで3mmの厚付けができませんでしたが、開発品の2液型では3mmが可能になりました。
次に厚膜性が高く肉やせが非常に少ないこと。例えば2mm塗った場合、従来品は乾燥すると1.3mmに肉やせしますが、開発品では1.8mmにとどまっています。
最も優れたメリットは速乾性です。2mm厚の場合、従来品では2~3日、あるいはそれ以上を要していたところ、開発品では12時間で乾燥してしまいます。
耐水性も数段アップし、柔軟性に関しても鉄骨追従性が従来より高まりました。
■塗料メーカー全体で耐火塗料市場の拡大を
このようなメリットがあれば、海外の耐火塗料のようにプレコーティングしやすくなると思います。
先ほどご覧に入れた海外企業の製品は、2㎥ほどもある大きな機械でしたが、当社の開発品は軽微なエアレスガンでの工事が可能です。このような吹付け適性も特徴の一つです(図6)。
2液型なので、ガン詰まりやローラー固化が懸念されるところですが、どちらも問題なく、連続施工が可能であるという試験結果も得ています。厚付け性・耐タレ性試験も実施しましたが、膜厚が小さくてもタレないという評価でした。
まとめると、鉄骨造の増加に伴って耐火被覆工事も増えているが、施工環境が悪く職人も減少しつつあるため耐火被覆工事の状況が改善できていない、というのが今現場が直面している問題です。しかし海外の市場を見渡せば、プレコートが主流で耐火塗料がたくさん使われています。
耐火塗料は、1993年から建設省総合技術開発プロジェクトで研究が進められ、2000年に実用化されるようになりました。着眼点はよかったのですが、それ以降20年経っても耐火塗料のシェアは伸びていません。
にもかかわらず、耐火被覆の現場では施工環境が悪化する一方です。今後、プレコーティングができる新しいタイプの耐火塗料の市場を拡大させることに注力したいと考えています。当社のみならず塗料メーカー全体で、海外企業とも協力しながら、日建連さまへのアプローチも進めながら、国に対して「こんなによいものがある」「このような製品で施工すれば、現場の省力化が進む」といったことを提案していきたいと考えています。
|
|
 |
「ICTを活用したコンクリートの情報化施工」
西島 茂行氏 児玉㈱ 執行役員 エンジニアリング事業部長
|
|
|
データが重いので右クリックしてメニューからファイルをダウンロードしてください
資料はこちら(PDFデータ)
|
|
|
■コンクリートを取り巻く時代背景と今後の指標
自動車業界、医学界、農業分野は、すでにICTを駆使して著しい進化を遂げつつあります。建設業界では、近年国交省から「i-Construcion」などが推奨されてはいるものの、まだまだ改革の余地があります。今後、省力化や省人化が望まれるなか、型枠などに複合センサを搭載し、配線や設置の手間を省き、無線で情報をモニタリングする手法などを導入することで、高度化、近代化した現場管理を目指す必要があります。
私は、この建材協会の顧問も務める東京大学大学院の野口貴文教授と8年前からICTを活用したコンクリート用センサの開発を始めました。
コンクリートは、打設直後から養生に大きく左右されます。若材齢コンクリートの品質管理(初期の養生)は長期耐久性能に影響を与える、極めて重要な要因です。ここで間違えると後でいかに手を加えてもよいコンクリートにはなりません。
しかし現実は、構造体の立地環境、用途、施工者の取り組み方などの違いから、徹底した若材齢コンクリートの品質管理は難しく、現場の状況判断に依存しています。型枠の向こう側で起きている水和反応の履歴やデータを、センサを駆使して時々刻々と記録できないだろうか、と考えたのがスタートです。
海外で実際に普及しているワイヤレスセンサを見ると、使い捨てタイプのものを鉄筋に巻きつけてコンクリートに埋め込み、そこから情報収集できる形をとっています。一方でこれは、コンクリートに「異物」を混入していることになります。鉄筋とコンクリートの膨張・収縮率はほとんど同じなので本来は問題ないのですが、このような異物(センサ)が埋設されるとクラックの原因になります。
これに代わるものとして、型枠の外側に搭載して繰り返し使えるセンサを開発しました(図1)。型枠に穴を空け、センシング部分だけを直接コンクリート表面から測定するもので、埋め殺しの必要がありません。型枠はコンクリートが固まれば役目を終えて外されるので、センサも同時に外せてまた利用できます。
■3種のセンサでコンクリート打設工程を検知し記録
内部には①加速度センサ、②静電容量センサ、③温度センサという3種のセンサが搭載され、コンクリート打設工程を検知し記録するという仕組みです。
具体的には、加速度センサで型枠の設置状況を感知し、静電容量センサで生コンの付着を感知してコンクリート打設を検知。温度センサで躯体表面温度を計測して水和反応の履歴を時々刻々ととらえ、その温度から強度発現を確認。強度が発現して型枠を外すと、その脱型状況も感知します。
今までは、テストピース(試供体)をつぶしの試験機まで持って行ってつぶすというアナログな方法で強度発現を確認していました。センサを使うと、現場にいながらにして、ピンポイントで強度が分かります。
図2は、実際に行われたトンネル工事のセントル(半円筒形の型枠)に使われたセンサから得た情報をグラフ化したものです。生コンが入って反応が始まり、脱型時にも動きが出ていることが分かります。
■センサ搭載型枠を形成するための条件
木製型枠、いわゆるコンパネにセンサを付けられないかとよく聞かれます。センサのセンシング部分は非常に敏感な部分。生コンの水分で木製型枠が膨張収縮を繰り返すと、センシング部にモルタルなどが付着してしまい、その結果測定値の信頼性が失われます。従って木製型枠には付けません。
そこで推奨しているのが樹脂型枠です。建築リサイクル法(2000年)が施行された当時、木製型枠(コンパネ)が大量に出回っており、同法施行の5年前、樹脂メーカー24社が協力して樹脂型枠で市場に参入しました。しかしながら、コンクリート躯体に気泡が発生する、型枠連結部からノロ漏れ(コンクリートが染み出すこと)して砂目地が発生するなどの問題があったため、ほとんど普及してきませんでした。
この問題を解決しようと、野口教授と研究を重ねました。おかげさまで非常に優秀な樹脂型枠がほぼ完成しつつあり、近日発表する予定です。
■実験により強度推定式を確立、建基法にも追記
「水和反応の温度測定からコンクリート強度が分かるはずがない」。8年前に研究をスタートしたとき、ゼネコンの方々からよくこう言われました。しかし熱力学的に、積算温度は圧縮強度と明らかに一定の関係性を持っています。ここから導き出された「有効材齢式」という計算方法は、コンクリートの力学特性に関する研究論文でも世界的に利用されています。
国際コンリート連合が品質管理のためのンクリートの圧縮強度推定式として採用しているほか、JC(I 日本コンクリート工学会)のマスコンクリートのひびわれ制御指針などにも有効材齢式が導入されています。材齢とは打設してからの日数のことで、有効材齢というからには有効でないものもあります。日数だけでなく温度も加味して有効な材齢だけをチョイスして当てはめたのが「強度推定式」です。これで強度が分かります。
2015年につくばの建築研究所で、強度推定法の適用に関する研究を行ってもらいました。土木では、コンクリートの標準示方書で日数管理から脱型と示されていますが、建築では建築基準法で規定されています。コンクリートの強度発現がコンクリートの水和反応時の温度と相関していることから、温度による強度推定を型枠脱型の判定に適用できるのではないかとして実施された実験です。
大きな試験体にセンサを取り付け、温度測定して強度推定するのですが、非常によい評価が出ました(図3)。結果は国交省の国土技術政策総合研究所(国総研)から発表され、2016年には建築基準法第76条第2項に強度推定式が追記されました。つまり「温度から強度を推定して脱型を判断してもよい」と法的に認められたのです。70年近く前に制定された建築基準法にこれが書き加えられたことは、非常に画期的な出来事でした。
■温度と強度をカラー表示でビジュアル化
図4の温度分布図を、一つのマス目を1枚の型枠と考えてご覧ください。各型枠にセンサが載っており、温度が表示されています。温度が変わるたびに強度も変わっていき、それがカラーで表示されます。テストピースの場合、部分的にしかデータが取れないので、ポイントによってばらつきが出るのですが、センサなら継続的に正確な強度が追跡できます。現場にいながら強度が分かるのはセンサの大きな利点でしょう。
「全ての型枠にセンサを搭載するのはオーバースペックではないか」という意見が現場から出ることがあったため、去年12月、野口教授の指導のもと、設置基準の見直し・改定を行いました。従来の全面搭載から、4隅と真ん中の最低5カ所搭載になり、かなり使いやすくなりました。これが1カ所ではやはりだめで、テストピースを使った破壊試験であっても1本だけでは信頼性が低いので、3本取ってつぶし、平均を取っています。
■今までできなかった確認がセンサによって可能に
野口教授との出会いは十数年前のことです。私は当時人生最大のピンチに陥り、仕事のない状況だったのですが、そこを今の会社に拾ってもらいました。窮地を助けられた思いから、私は何か人の役に立つことがしたいと強く考えるようになりました。この思いが野口教授とのご縁につながっていったと思います。
教授との研究のなかで、センサを使ったいろいろな計測方法を開発しました。例えば温度ひび割れの一元管理。コンクリートの一番外側と中心部の温度差を見るときにセンサを活用でき、それを一元管理することも可能です(図5)。
あるいは夏場のコンクリートで、パイプクーリングなどで温度差を調整しますが、その効果がどの程度あるのか確認することもできます。このようにコンクリートの温度確認を、「おそらくこうだろう」ではなく、しっかり記録して残すことができるようになります。
トンネル工事では、セントルの設置から打設位置の確認、水和反応の感知と記録を行い、若材齢の脱型強度を判定。圧力管理も大事で、圧力センサで確認します。こうした施工工程を一元管理・記録できるわけです。無線なので、有線のように断線の心配も不要です。
橋梁の例では、適性強度に基づく床版の脱型判断にも活用できます。例えばピア(橋脚)からピアに渡る桁や床版の底面は下方に引っ張られますが、下にセンサを付けておくことで、その部分の脱型判断ができます。おそらく必要強度に達したと思われるものの、テストピースでしか判断できていないのでもどかしい、という理由で活用していた現場もあります。
このように、今までできなかった確認がセンサによって可能になります。
■工期短縮、省人・省力化に貢献、生産性向上へ
センサシステム導入のメリットを整理してみました。
・緊張強度、ひび割れ対策の確認・検証・記録
・工期短縮・コスト削減も可能
・省人・省力化にも有効
・躯体そのものの強度管理ができる
・専用リーダで一元管理
実際にシステムを工期短縮などの効果につなげるには、使う人間が図面をしっかり読んで躯体を想像し、「どこにどのような形で取り付けるのが有効か」を考える必要があります。現在、ピアやトンネル、ダム、海洋土木(防潮堤、防波堤)などで使われています(図6)。
センシング技術や次世代型枠は現在、社会資本整備のための土木工事、いわゆる公共工事に盛んに投入されるようになりました。今後は建築分野でも、RC構造の現場打ちコンクリートの品質担保や、二次製品のPC工場などにおける品質証明など、コンクリートに限らず多方面にわたる建築材料のデジタル化が進むでしょう。生産性の向上と省力化へ向けて、ますます進化する建築材料と共に、センシング技術も共存共栄を図りたいと考えます。
|
|
|
[建材情報交流会ニュース一覧へ] |